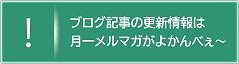( 香水工場の )
香る生活
香りの花:フジバカマ
平安貴族を彷彿させる優雅な香り (Updated:2025/07/18, Posted:2021/10/03)
 ( 秋の七草、藤袴 = フジバカマ )
( 秋の七草、藤袴 = フジバカマ )
いろいろな資料にフジバカマは中国~朝鮮半島原産とあり日本には奈良時代に伝えられ、その後日本の大地に帰化したとされる。
もともと日本列島は朝鮮半島と陸続きだった説が有力なので朝鮮半島が原産地なら日本原産の可能性もあるし、奈良時代以前にも日本土着というか日本固有のフジバカマがあってもおかしくないと思う。調べるとそういう説もあるようだ。
フジバカマは、万葉集や源氏物語にも登場するくらいで日本古来から日本人に親しまれた花ということは間違いない。
フジバカマは、中国でも愛される花で、漢名では「蘭草」「香草」「香水蘭」(Wikipedia)と表記されるそうで、名前の通り香りの花として認識されている。日本同様、匂い袋や入浴剤として利用されているという。
(それにしても「香水蘭」とは、本当にスーパー芳香植物と考えられているんですね・・)
平安時代の超絶・長編小説『源氏物語』は恋愛や宮廷内の政争などドロドロの人間模様を描いた世界的な古典だが、その中に「藤袴」というタイトルの「帖」(現代風に言えば「章」)がある。
藤袴帖では、夕霧(ゆうぎり)が父の光源氏(ひかるげんじ)の使いで玉鬘(たまかずら)のもとを訪れ、フジバカマの花を差し出すという場面がある(私は実際に読んでいないのでここは受け売り)。
悩める女性の心をいたわる描写をフジバカマによって象徴的に描いているな~と感じさせるクールな場面ではないか。そして実際の宮廷生活でフジバカマが利用されていたことがわかる章でもある。
フジバカマは着物の香り付けや室内の香り付けとして利用され、あるいは匂い袋の材料になっていたようだ。Wikipediaには「平安時代の女性は、藤袴の香を焚きこめて、香りを身につけていた」とあるが、みなさまの目の前に「藤袴の香を焚き」こめた女性が現れたら、まばゆいばかりにセクシーなことよ・・と感じられるだろう。
私は香水ビジネスに入る以前、フジバカマに関して名前も姿もまったく認知していなかった。
はじめて認識したのは20年くらい前、お香の老舗、京都「松栄堂」さんの店頭でのこと。エントランスでかすかな風に花を揺らしていた鉢植のフジバカマが咲いていた。小さな無数の花が素朴に可愛く、そして微かな香りを漂わせていた。
見とれていると「これがフジバカマです」と店員さんに説明された。ただし全体の形姿は「雑草?」と思う程度の普通の草だった。
(秋の七草とはそういうものである)とも思った。
しかしその香りをイメージした松栄堂さんのお香は和的で懐かしかった。聞けばフジバカマは奈良時代・平安時代の宮廷で愛されていた花・香りとのこと。はじめてフジバカマの名前を知り魅力を体験した。
お香の説明には、生花には香りはなく「花穂を刈り取って束ね、しばし陰干しにしてドライフラワーにすると、にわかに上品でみやびな香りを放つようになる」と書かれていた。
「源氏物語の薫の君や匂宮は、近づくとこんな匂いがしたのだろうか」という一文もあり空想をかき立てられた。
まあ、つまり雅で優雅な香りなのだ。
成分的にはクマリンが香りの特徴的な主体を担っているだけに桜餅のあの懐かしく情緒的な甘さに和んでしまう。
フジバカマの生花には香りはないとされるが、あのとき松栄堂さんのフジバカマに、私は確かに開花した花の香りを感じた気がした、今でもあれは何だったのか?と疑問のままである。
女王クレオパトラ7世は、宮廷をバラの花の香りで満たし、自身もバラ風呂に入り、バラの香油を全身に付け、その香りは多くの権力者たちを魅了したと伝えられている。
日本の平安貴族たちもフジバカマで宮中や自身を香らせた・・時代や場所は違っても案外似ている。
どの時代でも権力者がその権力と権威を誇示するためにファッションと香りは必須アイテムであることを人類の歴史は示している。
フジバカマの繁殖力は強く庭などに不用意に植えると地下茎が猛烈な勢いで拡大し制御不能に陥ると言った園芸愛好家さんの記事がネットで散見できる。
しかしそんなパワフルなフジバカマなのに、一方で絶滅危惧種に指定されている。河川の岸など湿った土地を好むフジバカマだが、なんでも護岸工事などで急速に生息地を失い数を減らしているという。
この説明はもっともに聞こえるものの疑問も感じる。生命力旺盛な植物は生息地が狭まっても荒れ地に生活圏を拡大するものだが、それができないということは、他の植物との競争力に弱いということではないか。
(人の場合も、このタイプ=競争力に弱い人は多い。日本人自体このタイプかも)
私は山野をよく歩く方だが、実際自生しているフジバカマにはなかなか出会わない。このまま減少してしまうと考えると、なんとも惜しい気持ちになる。
20年前、当社にはオードパルファム「藤袴(フジバカマ)」なる香水が存在した。
いつしかひっそりと廃盤となった。原料調達の問題で止めたのか、それとも人気不足でそうなったのか、今となっては定かでない。
20年前の『藤袴』はまだ早すぎたのかもしれない。今ならどうだろう?・・
処方はどこかに残っているだろう。原料がもし入手できるなら香水『藤袴』をリバイバル可能かもしれない・・
復活できればうれしいが、原料はおそらく入手不可で肝心の商業的な採算性と持続性は?・・おそらく厳しいだろう、こちらも悩める課題である。

(2025-07-18)
 ( 秋の七草、藤袴 = フジバカマ )
( 秋の七草、藤袴 = フジバカマ )東アジア原産?・・
いろいろな資料にフジバカマは中国~朝鮮半島原産とあり日本には奈良時代に伝えられ、その後日本の大地に帰化したとされる。
もともと日本列島は朝鮮半島と陸続きだった説が有力なので朝鮮半島が原産地なら日本原産の可能性もあるし、奈良時代以前にも日本土着というか日本固有のフジバカマがあってもおかしくないと思う。調べるとそういう説もあるようだ。
フジバカマは、万葉集や源氏物語にも登場するくらいで日本古来から日本人に親しまれた花ということは間違いない。
フジバカマは、中国でも愛される花で、漢名では「蘭草」「香草」「香水蘭」(Wikipedia)と表記されるそうで、名前の通り香りの花として認識されている。日本同様、匂い袋や入浴剤として利用されているという。
(それにしても「香水蘭」とは、本当にスーパー芳香植物と考えられているんですね・・)
源氏物語の中のフジバカマ
平安時代の超絶・長編小説『源氏物語』は恋愛や宮廷内の政争などドロドロの人間模様を描いた世界的な古典だが、その中に「藤袴」というタイトルの「帖」(現代風に言えば「章」)がある。
藤袴帖では、夕霧(ゆうぎり)が父の光源氏(ひかるげんじ)の使いで玉鬘(たまかずら)のもとを訪れ、フジバカマの花を差し出すという場面がある(私は実際に読んでいないのでここは受け売り)。
悩める女性の心をいたわる描写をフジバカマによって象徴的に描いているな~と感じさせるクールな場面ではないか。そして実際の宮廷生活でフジバカマが利用されていたことがわかる章でもある。
フジバカマは着物の香り付けや室内の香り付けとして利用され、あるいは匂い袋の材料になっていたようだ。Wikipediaには「平安時代の女性は、藤袴の香を焚きこめて、香りを身につけていた」とあるが、みなさまの目の前に「藤袴の香を焚き」こめた女性が現れたら、まばゆいばかりにセクシーなことよ・・と感じられるだろう。
フジバカマの思い出、初のフジバカマ
私は香水ビジネスに入る以前、フジバカマに関して名前も姿もまったく認知していなかった。
はじめて認識したのは20年くらい前、お香の老舗、京都「松栄堂」さんの店頭でのこと。エントランスでかすかな風に花を揺らしていた鉢植のフジバカマが咲いていた。小さな無数の花が素朴に可愛く、そして微かな香りを漂わせていた。
見とれていると「これがフジバカマです」と店員さんに説明された。ただし全体の形姿は「雑草?」と思う程度の普通の草だった。
(秋の七草とはそういうものである)とも思った。
しかしその香りをイメージした松栄堂さんのお香は和的で懐かしかった。聞けばフジバカマは奈良時代・平安時代の宮廷で愛されていた花・香りとのこと。はじめてフジバカマの名前を知り魅力を体験した。
甘く懐かしい香り
お香の説明には、生花には香りはなく「花穂を刈り取って束ね、しばし陰干しにしてドライフラワーにすると、にわかに上品でみやびな香りを放つようになる」と書かれていた。
「源氏物語の薫の君や匂宮は、近づくとこんな匂いがしたのだろうか」という一文もあり空想をかき立てられた。
まあ、つまり雅で優雅な香りなのだ。
成分的にはクマリンが香りの特徴的な主体を担っているだけに桜餅のあの懐かしく情緒的な甘さに和んでしまう。
フジバカマの生花には香りはないとされるが、あのとき松栄堂さんのフジバカマに、私は確かに開花した花の香りを感じた気がした、今でもあれは何だったのか?と疑問のままである。
宮廷&香り=世界の共通性
女王クレオパトラ7世は、宮廷をバラの花の香りで満たし、自身もバラ風呂に入り、バラの香油を全身に付け、その香りは多くの権力者たちを魅了したと伝えられている。
日本の平安貴族たちもフジバカマで宮中や自身を香らせた・・時代や場所は違っても案外似ている。
どの時代でも権力者がその権力と権威を誇示するためにファッションと香りは必須アイテムであることを人類の歴史は示している。
フジバカマ=絶滅危惧種
フジバカマの繁殖力は強く庭などに不用意に植えると地下茎が猛烈な勢いで拡大し制御不能に陥ると言った園芸愛好家さんの記事がネットで散見できる。
しかしそんなパワフルなフジバカマなのに、一方で絶滅危惧種に指定されている。河川の岸など湿った土地を好むフジバカマだが、なんでも護岸工事などで急速に生息地を失い数を減らしているという。
この説明はもっともに聞こえるものの疑問も感じる。生命力旺盛な植物は生息地が狭まっても荒れ地に生活圏を拡大するものだが、それができないということは、他の植物との競争力に弱いということではないか。
(人の場合も、このタイプ=競争力に弱い人は多い。日本人自体このタイプかも)
私は山野をよく歩く方だが、実際自生しているフジバカマにはなかなか出会わない。このまま減少してしまうと考えると、なんとも惜しい気持ちになる。
香水『藤袴』復活は?
20年前、当社にはオードパルファム「藤袴(フジバカマ)」なる香水が存在した。
いつしかひっそりと廃盤となった。原料調達の問題で止めたのか、それとも人気不足でそうなったのか、今となっては定かでない。
20年前の『藤袴』はまだ早すぎたのかもしれない。今ならどうだろう?・・
処方はどこかに残っているだろう。原料がもし入手できるなら香水『藤袴』をリバイバル可能かもしれない・・
復活できればうれしいが、原料はおそらく入手不可で肝心の商業的な採算性と持続性は?・・おそらく厳しいだろう、こちらも悩める課題である。

(2025-07-18)
search